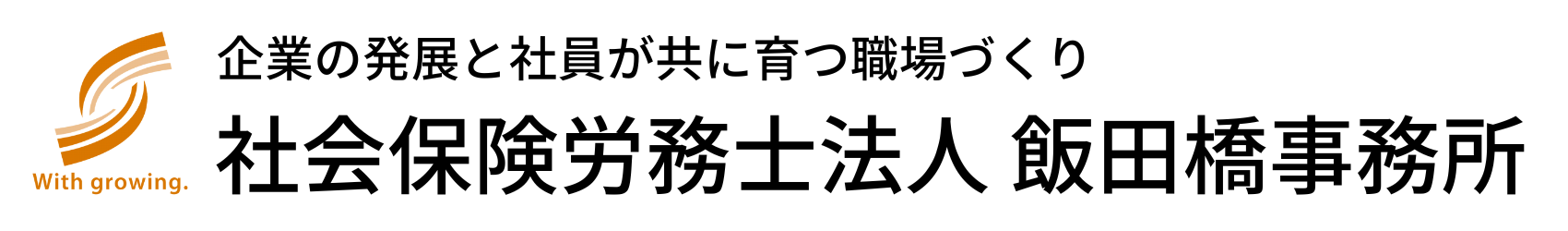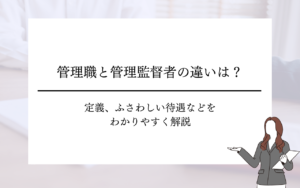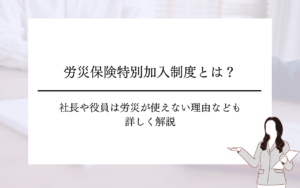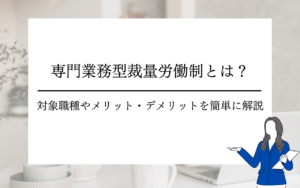2019年4月施行の働き方改革では、時間当たりの生産性を意識した効率的で柔軟な働き方に変えていくことが求められます。
特に人手不足が深刻な中小企業にとっては、限られた労働力をどのように活用していくのかを考えなければなりません。そこに立ちはだかる大きな課題、それが労働時間です。
未払い残業代、過労死や過労自殺、メンタルヘルスなどは、労働時間を正しく管理していないことで起こりうる問題です。
今回は、この労働時間の基本について解説いたします。

労働時間は3種類ある!?
労働時間には大きく分けて「所定労働時間」 「法定労働時間」 「実労働時間」の3つがあります。
労働時間を管理していくうえで、これらの正しい内容を確認していきましょう。
「所定労働時間」について
所定労働時間とは、労働契約で定められた労働時間です。
所定労働時間は、一般的には就業規則や労働契約書で定められます。会社の定めた始業時刻から終業時刻までの時間を拘束時間といい、拘束時間から休憩時間を除いた時間が所定労働時間となります。
所定労働時間=始業時刻~終業時刻(拘束時間)-休憩時間
例えば、始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩1時間と定められている場合、所定労働時間は8時間となります。
なお、休憩時間については、労働時間が6時間を超えて8時間未満の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間与えなければならないとされています(労基法34条)。所定労働時間が8時間の場合は、休憩時間を少なくとも45分以上として定める必要があります。
「法定労働時間」について
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間です。
労働基準法(以下、「労基法」という。)32条では、休憩時間を除き、1週間について40時間(※)、1日について8時間を超えて労働させてはならないとなっています。
そのため、後述する1-3の実労働時間は、原則として、法定労働時間を超えることができません。法定労働時間を超えて労働させる場合は、事前に時間外労働・休日労働に関する協定届(以下「36協定」という。)を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
また、1-1の所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で定めなければなりません。
例えば、始業時刻が8時、終業時刻が18時、休憩1時間と定められていた場合、所定労働時間は9時間となり、法定労働時間の8時間を超えてしまいます。
所定労働時間(9時間)>法定労働時間(8時間)
この場合、8時間を超えた部分(1時間)は所定労働時間として無効となり、所定労働時間は8時間に強制的に修正されます(労基法13条)。
したがって、この場合、8時間を超えた1時間は時間外労働(いわゆる残業時間)となり、割増賃金の対象となります。
※常時10人未満の労働者を使用する一定業種(特例事業場)については44時間。
「実労働時間」について
実労働時間とは、使用者が労働者を労働させた時間です。
実労働時間については、労基法による定義はありません。判例(三菱重工業長崎造船所事件判決)では、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。
使用者の指揮命令下に置かれていたか否かについては、「使用者による義務付け」もしくは「余儀なくされる」(やらざるを得ない)状態にあったかが主な基準として判断されています。
例えば、始業時刻前のラジオ体操の時間が労働時間か否かといった問題があったとします。この場合、ラジオ体操への参加が任意であれば労働時間ではなく、参加が義務付けられている、もしくは参加しないと人事考課などで不利益を被る場合は、参加することを余儀なくされていたとして労働時間と評価されます。
また、この指揮命令下にあるか否かについては、明示の指揮命令はもちろんのこと、黙示の指揮命令も含まれます。例えば、残業命令(許可)をしていない従業員が居残って残業をしていたケースで、そのことを上司が知っていた(黙認している、明示の残業禁止をしていない)場合、黙示の残業命令があったとみなされ労働時間と評価されることがあります。

まとめ
労働時間には大きく分けて「所定労働時間」「法定労働時間」「実労働時間」の3つあることがお分かりいただけたでしょうか。
日々の労働時間規制では、実労働時間を把握することが特に重要です。未払い残業代の問題は、把握されていない隠れた実労働時間が浮き彫りにされた結果です。過労死や過労自殺、メンタルヘルスなどの問題はこの実労働時間が長いことが影響しています。
長時間労働は、労働者の心身を疲弊させ、企業の労働生産性を低下させる要因となります。働き方改革では、労働時間の「長さ」ではなく、労働時間の「質」を高める働き方に転換していくことが求められるでしょう。
(注)この記事の内容は、2019年8月1日現在の法令等によります。
社会保険労務士 横島洋志