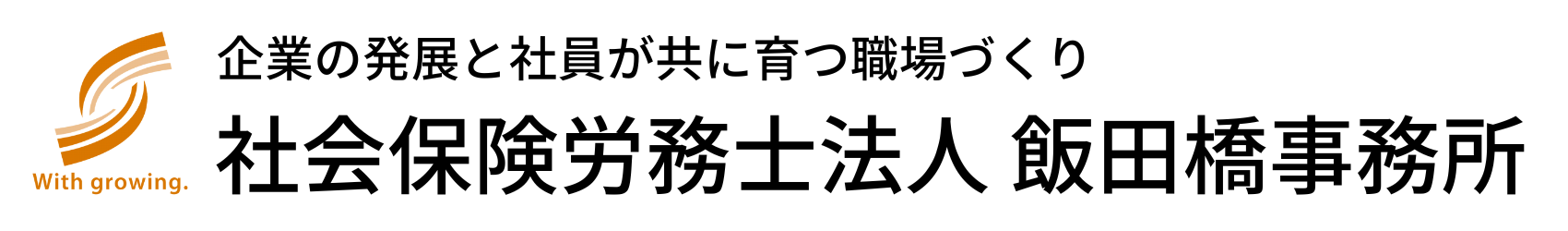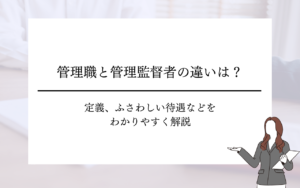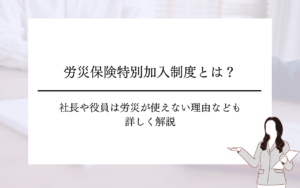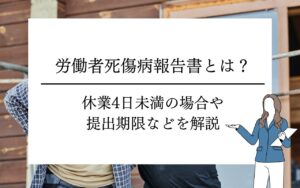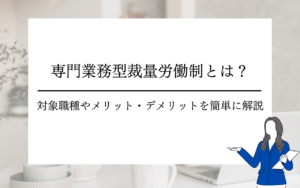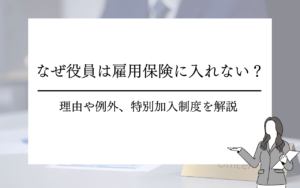2025年の育児・介護休業法改正により、育児・介護と仕事の両立支援を強化する新たなルールが導入され、企業は従業員のワークライフバランスの見直しや適切な対応を求められます。
本改正に対応するためには、企業の制度整備や従業員への周知が重要です。
この記事では、育児・介護休業法改正の具体的な内容と企業が今すぐ取り組むべきポイントをわかりやすく解説します。
育児・介護休業法とは?

育児・介護休業法(正式名称:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)は、仕事と家庭の両立を支援するための法律です。
かつては、育児や介護のために仕事を辞めざるを得ないケースが多く、労働者は仕事か家庭かの二者択一を迫られていました。
このような問題を解決することを目的に、本法律は労働時間の短縮や給付金の支給などの支援策を設け、ワークライフバランスを実現することを目指しています。
参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律|厚生労働省
参考:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内|厚生労働省
【2025年施行】育児・介護休業法改正のポイント

2025年の育児・介護休業法改正では、育児や介護と仕事を両立しやすい環境を整えるための措置が強化されます。
就業規則の変更を伴わないものの、事業主が対応しなければならない措置として、雇用環境整備・個別の周知・意向確認・意見聴取配慮が求められます。
①子の看護等休暇の見直し
2025年施行の育児・介護休業法改正に伴い、「子の看護休暇」が大幅に見直され、名称も「子の看護等休暇」へ変更されました。
この改正は、働く親がより柔軟に子どもの看護に対応できるよう、対象範囲や取得事由、除外規定が見直されることを目的としています。具体的には、次のような変更点があります。
●対象となる子の範囲の拡大
| 施行前 | 小学校就学の始期に達するまで |
|---|---|
| 施行後 | 小学校3年生修了まで |
●取得事由の拡大
| 従来 | 病気・けが、予防接種・健康診断 |
|---|---|
| 新たに追加 | 感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式 |
●除外規定の変更
| 従来 | 週の所定労働日数が2日以下、継続雇用期間6か月未満の場合に除外 |
|---|---|
| 施行後 | 除外対象は週の所定労働日数が2日以下(継続雇用期間の条件は撤廃) |
このように、改正により休暇の対象となる子どもの範囲が広がり、従来よりも多様な理由で休暇が取得可能となります。
また、除外規定の簡素化により、短期間の雇用条件にある労働者でも一定の条件下で休暇が利用できるようになるため、制度全体の公平性と実効性が向上することが期待されます。
②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
2025年施行の育児・介護休業法改正により、所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大され、働く親にとってより利用しやすい制度となります。
従来は、残業免除の請求が3歳未満の子を養育する労働者に限定されていましたが、改正後は小学校就学前の子を養育する労働者にもこの対象が広がります。
これにより、対象となる労働者の幅が拡大され、育児と仕事の両立を図るための柔軟な働き方がより実現しやすくなります。
| 施行前 | 残業免除の対象は、3歳未満の子を養育する労働者 |
|---|---|
| 施行後 | 残業免除の対象が、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大 |
この改正は、育児の状況に応じた残業免除の適用範囲の見直しにより、子育て中の労働者がより働きやすい環境を整えることを目的としています。
③介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
従来、介護休暇の適用にあたっては、労使協定に基づき「週の所定労働日数が2日以下」と「継続雇用期間が6か月未満」の除外条件が設けられていました。
改正後は、「継続雇用期間6か月未満」という条件が撤廃され、除外対象は「週の所定労働日数が2日以下」のみとなります。
| 改正前の除外条件 | ・週の所定労働日数が2日以下 ・継続雇用期間が6か月未満 |
|---|---|
| 改正後の除外条件 | 週の所定労働日数が2日以下(継続雇用期間の条件は撤廃) |
これにより、たとえば、継続雇用期間が6か月未満であっても、週に3日以上勤務している労働者は介護休暇を取得できるようになります。
この変更により、介護休暇制度はより柔軟かつ公平に運用されるようになり、短期間雇用の労働者でも一定の勤務日数が確保されていれば介護休暇の取得が可能となります。
④柔軟な働き方を実現するための措置等
令和7(2025)年10月1日施行の改正では、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、以下の5つの措置の中から2つ以上を選択して講ずることが義務付けられています。
労働者は、事業主が提供する2つの措置の中から1つを選んで利用することができます。また、措置選定時には過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日以上/月)
- 保育施設の設置運営等
- 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
- 短時間勤務制度
措置の具体例として、始業時刻の変更(フレックスタイムや時差出勤)、テレワーク(1ヶ月に10日以上の利用が可能なもの)、保育施設の設置や運営、養育両立支援休暇の付与(年10日以上)、短時間勤務制度(例:1日の労働時間を原則6時間)などがあります。2と4は原則時間単位で取得可とする必要があります。
企業における育児・介護休業法改正の対応ポイント

2025年の育児・介護休業法改正に向けて、企業には社内制度の整備や従業員への周知、業務環境の見直しなど、さまざまな対応が求められます。
従業員が育児・介護と仕事を両立しやすい環境を整えることは、法令遵守だけでなく、人材の定着や企業の魅力向上にもつながるでしょう。
ここでは、企業における育児・介護休業法改正の対応ポイントを解説します。
社内規則の見直しと整備

2025年の育児・介護休業法改正に伴い、企業は社内規則を見直し、最新の法改正に適合させる必要があります。
また、従業員が育児・介護休業を申し出やすい環境を整えるため、個別の周知や意向確認の仕組みを規則に明記しても良いでしょう。
以下で企業における育児介護休業法の改正で義務対象となる、雇用環境整備と周知意向確認等の概要を紹介します。
⑤介護離職防止のための「雇用環境整備」
事業主は、介護休業や介護両立支援制度の申出が円滑に行われるよう、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用事例の収集・提供
- 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
事業主は、上記1~4のうち、少なくとも1つの措置を講じる義務があります。
⑥介護に直面したときの「個別の周知・意向確認」
介護に直面した労働者に対し、事業主は以下の事項を個別に周知し、意向確認を行う必要があります。
- 介護休業・介護両立支援制度等の内容
- 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
- 介護休業給付金に関する情報
個別周知・意向確認の方法には、面談、書面交付、FAX、電子メールなどが含まれます。
⑦仕事と育児の両立に関する「個別の意向聴取・配慮」
事業主は、妊娠・出産等の申出があったときや、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、以下の事項について個別に意向を聴取しなければなりません。
- 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
- 勤務地(就業場所)
- 両立支援制度等の利用期間
- 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量や労働条件の見直し)
聴取した意向を踏まえ、事業主は自社の状況に応じた配慮を行う義務があります。
意向聴取の方法は、面談、書面交付、FAX、電子メール等が可能です。
2025年の改正では、上記の義務の対象企業が拡大される可能性があるため、中小企業を含む幅広い企業が早めに準備を進めることが重要です。
他企業の成功事例を活用した施策の導入

2025年の育児・介護休業法改正に対応するため、他企業の成功事例を参考にしながら、自社に適した施策を導入することが有効です。
以下では、育児休業の取得促進に関する成功事例と介護と仕事の両立支援に関する成功事例からみた有効な施策について解説します。
育児休業の取得促進に関する成功事例
厚生労働省の「育児休業取得企業好事例集(令和5年度版)」では、男性の育児休業取得促進に成功した企業の取り組みが紹介されています。
これらの事例から、以下のような施策が有効であることが分かります。
| 職場の雰囲気づくり | ・管理職向けに育児休業取得を支援する研修を実施・育児休業を取得しやすい文化を醸成するため、取得経験者のインタビューや座談会を社内で共有 |
|---|---|
| 取得しやすい制度設計 | ・育児休業を短期間(例:1週間単位)から取得可能にし、分割取得を推奨・休業中の代替業務を明確化し、チームでカバーする体制を構築 |
| 職場復帰支援の強化 | ・育児休業者向けの定期的なフォローアップ面談を実施・復帰後の働き方について事前に相談できる制度を導入 |
介護と仕事の両立支援に関する成功事例
介護と仕事の両立支援事例では、介護離職を防ぐために企業が取り組んでいる成功事例が紹介されています。主な施策として、以下のとおりです。
| 介護に関する情報提供 | ・社内ポータルサイトで相談窓口や支援制度を案内・外部の介護支援サービスと提携し、従業員が無料で相談できる環境を整備 |
|---|---|
| 柔軟な働き方の提供 | ・時短勤務やテレワークを活用し、介護と仕事を両立できる環境を整備・介護休業だけでなく、短時間勤務や在宅勤務との組み合わせを可能にする |
| 介護コミュニティの形成 | ・介護経験者同士が情報交換できる場を社内で設置・介護と仕事の両立支援をテーマにしたセミナーを定期開催 |
これらの成功事例を活用することで、企業は育児・介護の支援制度をより実効性のあるものにすることができます。
まとめ
2025年の育児・介護休業法改正では、育児休業の取得促進と柔軟な働き方の導入、介護離職防止のための企業支援強化がポイントとなります。
育児休業の取得状況の公表義務の拡大が予定されており、中小企業も対象となる可能性があるため、早めの準備が重要です。
企業は法改正を見据え、社内制度の整備や従業員への周知を進めることで、職場環境の改善と人材定着の強化を図ることが求められます。