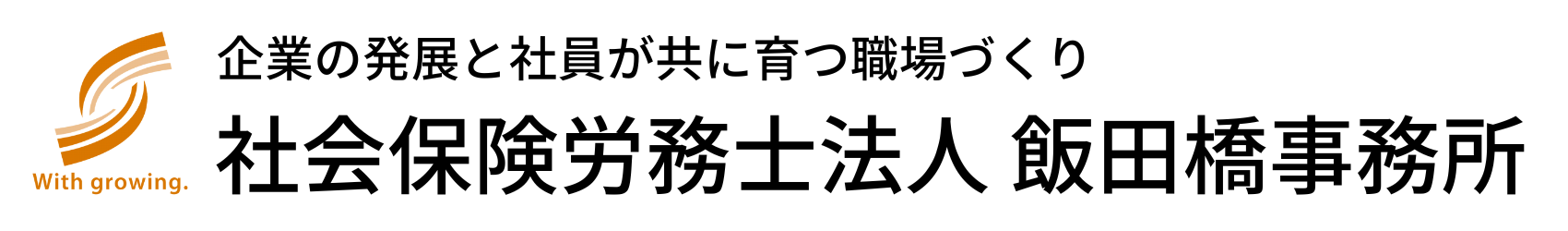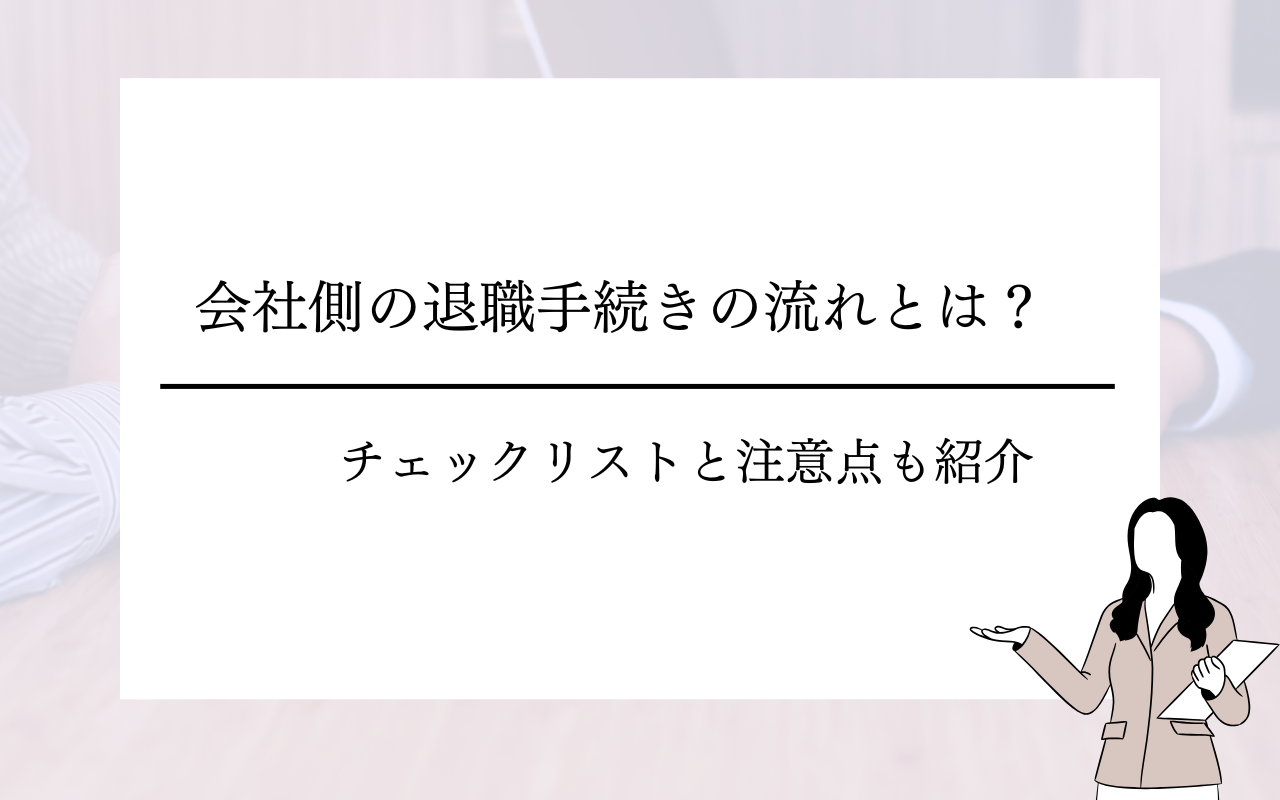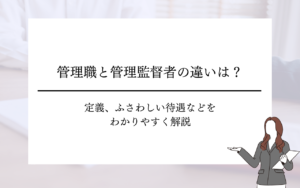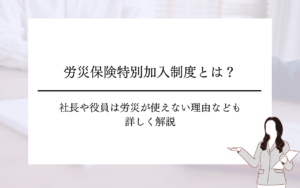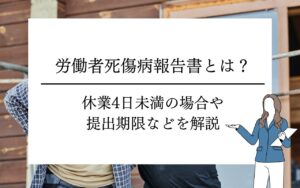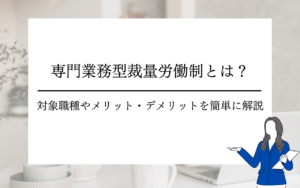従業員が退職を申し出た際、会社側には適切な手続きを行う義務があります。
退職日までの対応がスムーズでないと、引き継ぎの遅れやトラブルの原因となる可能性もあるため、事前に正しい流れを把握しておくことが重要です。
本記事では、会社側が行うべき退職手続きの基本的な流れと注意点について解説します。
会社側の退職手続きの流れ

会社側の退職手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。
- 退職届の受理
- 貸与物や健康保険証の回収
- 社会保険の資格喪失手続き
- 雇用保険の資格喪失手続き
- 所得税・住民税の手続き
- 退職者への書類発行・郵送
ここでは、退職届の受理から、社会保険や雇用保険の手続き、各種証明書の発行・送付までの一般的な流れを説明します。
退職届の受理
従業員が退職を申し出た際、会社は適切な手続きを進める必要があります。
退職の申し出には、契約形態や労働契約の種類によって異なるルールが適用されるため、事前に確認して対応することが重要です。
退職の申し出に関する基本ルールは、労働契約期間の定めの有無によって異なります。
正社員などの期間の定めがない雇用契約の場合、民法第627条第1項に基づき、従業員は退職予定日の2週間前までに申し出ることで、いつでも退職が可能です。
会社の就業規則に「1ヶ月前までに申し出ること」と定められている場合でも、法律上は民法の規定が優先されます。
アルバイトや契約社員などの有期労働契約(原則として上限3年)の場合には、契約期間の満了をもって労働契約が終了します。しかし、原則的な有期労働契約の場合、契約日から1年を経過した日以降は、従業員は使用者に申し出ることによって、いつでも退職できます(労基法付則第137条)。
なお、やむを得ない事由がある場合は、契約日から1年未満であっても期間途中の退職が認められています(民法第628条)。
参考:第5章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき|厚生労働省
貸与物や健康保険証の回収
従業員が退職する際、会社から貸与していた物品の返却や健康保険証の回収を確実に行う必要があります。
これを怠ると、退職後に回収の手間がかかったり、仕事内容によっては機密情報の漏洩リスクが生じたりする可能性があるため、計画的に対応しましょう。
退職する従業員が最終出勤日までに返却するべき貸与物には、以下のようなものがあります。
- 社員証・名刺
- PC・スマートフォン・タブレット
- 制服・作業着・備品
- 作成資料・業務データ
また、退職日の翌日をもって、従業員の健康保険の資格が喪失するため、健康保険証(扶養家族分も含む)を必ず回収し、会社が管轄の年金事務所へ返却手続きを行う必要があります。
詳しくは後述しますが、健康保険の資格喪失手続きは、退職日の翌日から5日以内に年金事務所へ「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」とともに健康保険証を提出する必要があるためです。
社会保険・雇用保険の資格喪失手続き
退職した従業員の健康保険および厚生年金保険の資格喪失手続きは、会社が速やかに行う必要があります。
従業員が退職・死亡または契約変更などにより、健康保険・厚生年金の資格を喪失した場合、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出します。
- 資格喪失日を確認
- 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」の提出
- 健康保険証の回収・提出
添付書類として、以下のいずれかを提出します。
- 退職辞令の写し・就業規則
- 雇用契約書の写し
- 退職日と再雇用日の事業主証明書
所得税・住民税の手続き
退職者の所得税・住民税の手続きは、会社側が適切に対応する必要があります。
住民税は退職のタイミングによって徴収方法が異なるため、注意が必要です。
会社は、退職者に対して源泉徴収票を発行しなければなりません。これは、退職者が確定申告や転職先での年末調整を行う際に必要な書類です。
| 源泉徴収票の発行期限 | 退職後1ヶ月以内 |
|---|---|
| 交付方法 | 手渡しまたは郵送 |
源泉徴収票の発行が遅れると、所得税法に基づく罰則が科される可能性があるため注意が必要です。
また、住民税は、1月1日時点で住んでいた市区町村に納める義務があります。退職後の住民税の支払い方法は、退職時期によって異なります。
1~5月の年度途中に退職する場合の住民税未払い分は、退職時の給与や退職金から一括徴収する必要があり、会社が退職月の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に提出する必要があるため注意しましょう。
6~12月に退職する場合には、退職者が自分で住民税を納付(普通徴収)するか、退職時に一括徴収するかを選択できます。
一括徴収しない場合、退職者が市区町村から送付される納付書で、年4回に分けて住民税を納付することになります。
参考:源泉徴収のしかた|国税庁
参考:住民税の特別徴収にご協力ください!|総務省
退職者への書類発行・郵送
退職者には、退職後に必要となる各種書類を適切な期限内に発行・郵送する必要があります。
源泉徴収票や離職票は転職や失業給付の申請などに必要な書類のため、遅れのない対応が求められます。
以下は必要な書類と、その対象者と発行期限です。
| 書類名 | 必要な退職者 | 発行期限 |
|---|---|---|
| 源泉徴収票 | 全員 | 退職後1ヶ月以内 |
| 雇用保険被保険者証 | 雇用保険加入者 | 退職日までに |
| 離職票(離職票-1・離職票-2) | 失業給付を申請する人 | 退職後10日以内 |
| 退職証明書 | 希望者のみ | 速やかに発行 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険に加入する人 | 申請後速やかに |
なかでも源泉徴収票や離職票の発行遅れは、退職者の不利益につながる可能性があるため、スムーズな手続きを心がけましょう。
参考:雇用保険被保険者離職証明書についての注意|厚生労働省
参考:No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|国税庁
会社側の退職手続きのチェックリスト
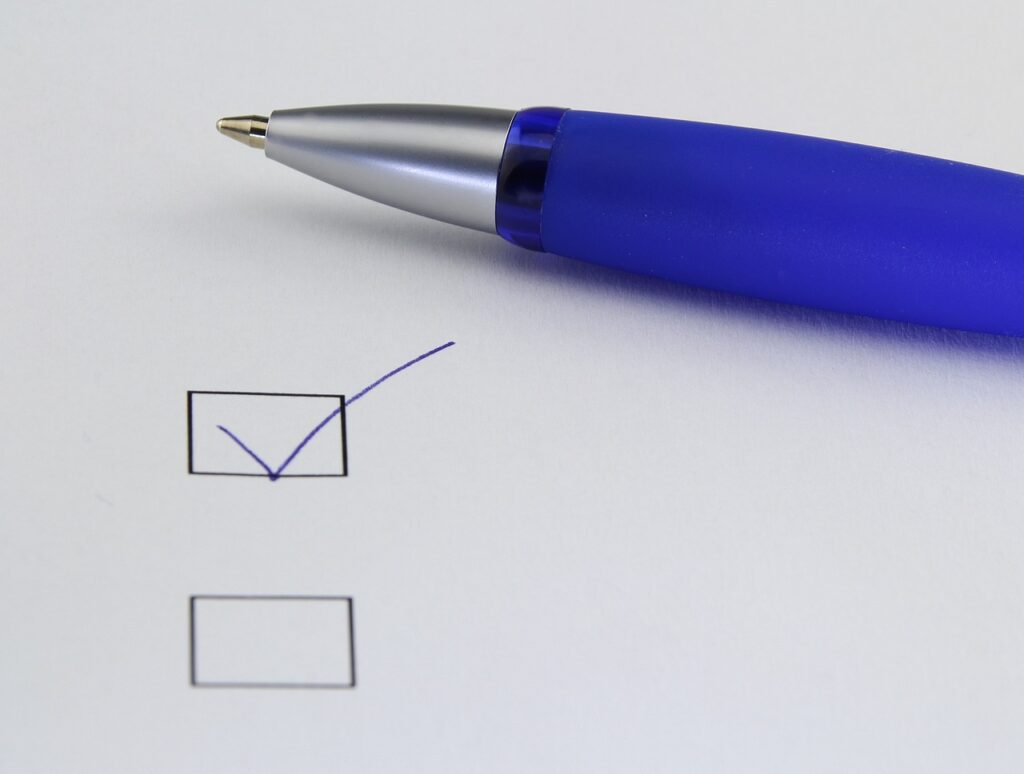
退職手続きをスムーズに進めるために、以下のチェックリストをご活用ください。
各項目を確認しながら対応することで、手続き漏れやトラブルを防ぐことができます。
必要に応じて関係部署と連携し、適切なサポートを行いましょう。
会社側の退職手続きの注意点

ここでは、会社側の退職手続きの注意点を以下のポイントで解説します。
- 退職届の受理時の注意点
- 未払い給与・有休消化の対応
- 退職者とのトラブル回避
それぞれで気になる部分をご確認ください。
退職届の受理時の注意点
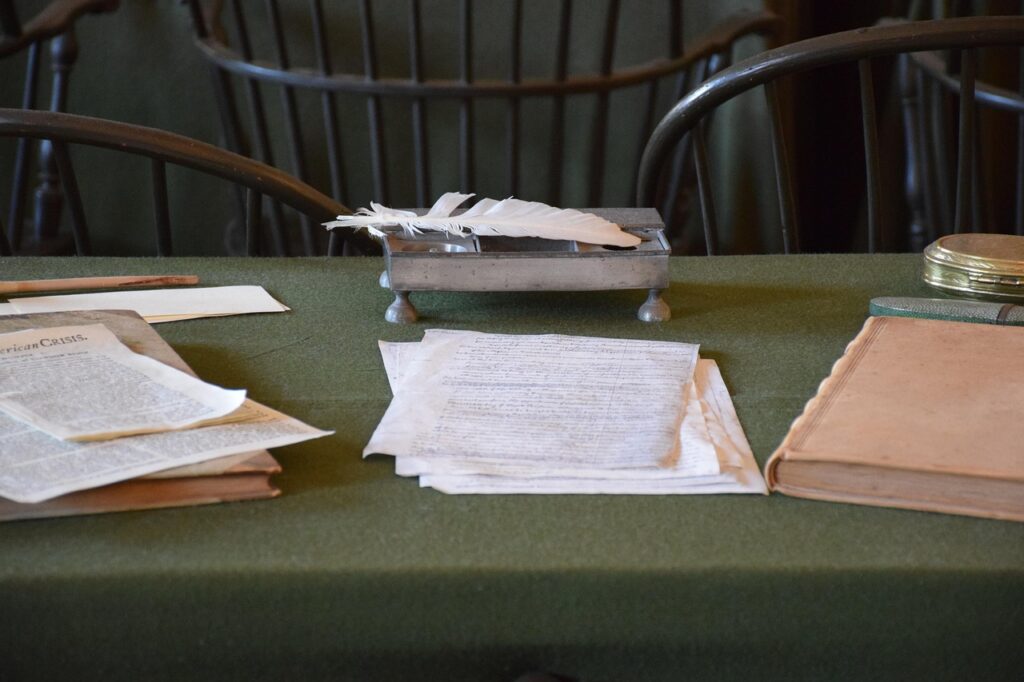
退職届を受理する際には、会社側として適切に対応しなければ、後々のトラブルにつながる可能性があります。以下のポイントに注意しながら、円滑な退職手続きを進めましょう。
- 退職の意思を正確に確認する
- 退職届は書面で提出してもらう
従業員が提出する退職届は、本人の自由な意思に基づいている必要があります。上司や同僚からの圧力による退職の強要がないかを確認し、もし疑いがある場合は慎重に対応しましょう。
また、口頭での退職の申し出は法律上有効ですが、後から「言った・言わない」のトラブルになる可能性があります。そのため、必ず書面で退職届を提出してもらうことが望ましいです。
退職届には以下の内容を記載してもらうようにしましょう。
- 退職する旨の明確な意思表示(例:「一身上の都合により退職します」)
- 退職日
- 本人の署名または押印
退職届には「一身上の都合」と記載するのが一般的ですが、会社都合退職(リストラや会社側の事情による解雇)の場合は、離職票に記載する退職理由と一致させる必要があります。
退職理由を誤って処理すると、従業員が失業給付を受け取る際に不利益を被ることもあるため、慎重に確認しましょう。
未払い給与・有休消化の対応
退職する従業員には、未払い給与や未消化の有給休暇(以下、有休)の適切な対応が必要です。
労働基準法の規定を守りつつ、円満な退職となるよう適切に手続きを進めましょう。
退職手続きに関わる労働基準法の規定には、以下のものがあります。
| 労働基準法の規定 | 関連する労働基準法の条文 | ポイント |
|---|---|---|
| 未払い給与の支払い義務 | 労働基準法第11条、第24条 | 賃金は全額・遅滞なく支払う。※最終給与の控除は要注意 |
| 有給休暇の消化 | 労働基準法第39条 | 労働者の権利会社は業務に支障がない限り拒否できない |
| 退職時の賃金精算 | 労働基準法第23条 | 労働者の請求があれば7日以内に支払う義務あり |
| 退職時のトラブル防止 | 労働基準法第104条 | 労働基準監督署に申告されるリスクを考慮し、適正対応が必要 |
賃金は給与、賞与、手当などすべてを含むため、退職時に未払いの給与や残業代があれば、必ず支払う必要があります。
有休の取得は労働者の権利であり、退職日までに消化するのが原則です。
労働者からの申請が必要ではあるものの、会社側は業務に支障がない限り有休取得を拒否できないため気をつける必要があります。
退職者とのトラブル回避

退職時には、退職者と会社の間で認識のズレが生じることがあり、トラブルに発展するケースも少なくありません。
トラブルを回避するために、以下のポイントを押さえて対応しましょう。
- 退職後の問い合わせ窓口を設ける
- 感情的な対立を避ける
退職者から源泉徴収票や退職証明書の発行依頼、社会保険の手続きに関する問い合わせなどが発生することがあります。
事前に担当部署や窓口を案内しておくことで、退職後のスムーズな対応につながるでしょう。
また退職に至る経緯によっては、退職者が会社に不満を持っている場合もあります。
しかし感情的な対立は双方にとってデメリットしかありません。
「お世話になりました」「これからのご活躍をお祈りします」 などのポジティブな姿勢を示すことで、円満な関係を目指すことができます。
まとめ
退職手続きを円滑に進めるためには、適切な対応と確認が重要です。
退職届の受理から貸与物の回収、社会保険・税金関連の手続き、必要書類の発行・郵送まで、各ステップを漏れなく進めることで、退職者とのトラブルを防ぐことができます。
また、未払い給与や有休消化の対応にも注意し、労働基準法を遵守しながら適切に対応しましょう。
スムーズな退職手続きは、企業の信頼にも関わるため、チェックリストなどを活用しながら確実に進めましょう。